■頭の中のイメージを絵にする■
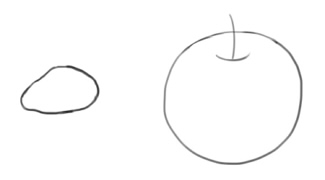
例えば、石ころやリンゴを "ただ漠然と" 描くとこんな感じです。
石ころは「小さくてでこぼこ、物によっては平たい」
リンゴは「丸くて赤い果物で、ヘタが付いている」
とりあえず、大雑把なイメージを文にするとこうなるのですが、このイメージで描くとこうなってしまいます。
まあ、落書きとか"あたり"で描くならこれくらいテキトーでもいいのですが、
ちゃんとした絵を描く時にイメージの段階でこれだと、完成後もこのまま質が上がりません。
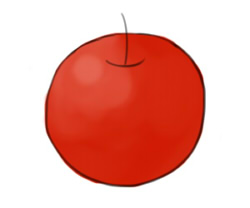
仮に上のリンゴにさっきのイメージのまま色を塗ってみましょう。
「リンゴは赤い」わけですから、とりあえず赤で塗って、丸いから、とりあえず軽く陰影でも付けてこんな感じ。
でも、これは多分リンゴを描いたと分かるけど、ちゃんと真面目にリンゴを描いてる感じではないですよね。
ヘタの部分を短く描いてしまったサクランボにも見えるし、赤色の爆弾っぽくも見えます。
これは、絵を描く時に、描くものを具体的にイメージしてないからこうなってしまうわけです。
リンゴをよりリンゴらしく描くためには、より具体的なイメージが必要です。
そしてその具体的なイメージとは"描く前の段階"で構築されるものでもあります。
描きながらイメージが膨らむこともありますが、それもやはりそのイメージを固めてから絵に起こしているものです。
ここで、赤リンゴのイメージを具体的に文に起こしてみましょう。
リンゴは確かに丸いけど、てっぺんの部分と底の部分は凹んでいます。
また、実も上の方が膨らんでいて下は少しすぼんでいて、どちらかと言うと、丸まったピーマンのような形をしています。
大きさや形に個体差もあります。
ヘタには太さがあり、先の部分は少し膨らんでもいます。
色についても、ただ赤いというわけではなく、面に沿って黄色やオレンジの縦の筋がいくつも入っていて、細かい斑点もあります。
上の凹みの周りはカーブがきつく、その周辺には光沢が生まれます。
こんな感じで、リンゴとは具体的にどんなものかを脳内でイメージしておいて、そのイメージを念頭に置きながら絵を描くことで、
よりリアリティのあるリンゴが描かれていくわけです。
ちなみに、実はサクランボもリンゴと似たような形をしています。
